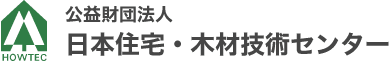木造建築新工法性能認証制度
◇制度概要
1.はじめに
| 経済社会が成熟化し国際化する中で、新たな産業構造を構築するための技術革新が強く求められています。木造建築・木材産業においても、耐震性などの高性能化、省エネ、長期耐用などの問題解決に向けた技術革新への取組みを強力に行うことが必要になっています。 しかし、木造建築・木材産業の場合、企業等が開発した工法及び部品・部材は、その品質・性能の評価が難しいことから、実際に使用されるようになるには、長い年月を要するものもあります。 このため、技術開発とその成果物の普及を促進させるためには、ネックとなっている品質・性能評価の困難さを解消するための社会的なシステムを構築することが重要となっています。 本認証制度は、以上のような観点から、企業等が開発した木造建築物の新しい工法や部品・部材の品質・性能を認証します。 なお、認証にあたっては、中立的な立場にある学識経験者で構成する認証委員会による審査を行います。 |
2.目的
| 技術開発された木造建築物の工法や部品・部材の性能に係る認証による品質性能及び生産性の向上を通じ、消費者の安全、安心等に寄与することを目的とします。 |
3.認証の概要
| (1)認証の対象 新工法性能認証の適用範囲は、次のとおりです。 1)適用建築物:木造建築物 2)認証の種類:企業等が技術開発した工法及び部品・部材 3)認証の区分:認証の区分は次の3区分(図1参照) ①試験法評価 ②性能証明 ③適合認証 4)認証の分野:認証の分野は次の3区分(図2参照) ①構造性能認証 ②省エネ性能認証 ③耐久性能認証 |

(2)認証の区分
認証の区分の概要は、次の①~②のとおりです。
①試験法評価
・新工法性能証等の開発を行うための工法及び部品・部材の試験方法等についての評価です。
・評価は、構造、省エネ及び耐久性に関する試験法評価です。
・評価の有効期限は、ありません。
②性能証明
・個別物件の性能を認証します。
・認証の種別は、工法及び部品・部材です。
・認証の分野は、構造性能認証、省エネ性能認証及び耐久性能認証です。
・認証の有効期限は、ありません。
ただし、部品・部材で性能及び品質を確保するために、工場の品質等を担保する必要がある場合は、この限りではありません。
③適合認証
・当センターが制定した工法及び部品・部材ですが、まだ制定に至っていません。
・認証の有効期限は、3年です。
(3)認証の分野と申請例
認証の区分、種類及び分野に対する申請の例は、図3のとおりです。
これらは、構造性能認証委員会、省エネ性能認証委員会及び耐久性能認証委員会で審議します。
(4)認証の対象外となるもの
当該認証で認証できないものは、以下のとおりです。
①建築基準法及び品確法令に基づく認証と重複する認証
②JAS、JIS及びAQ認証制度による認証と重複する認証
③現状の技術水準、その他の事情からその品質・性能を評価することが困難な認証
(5)認証等の流れ
認証等の主な流れは、図4のとおりです。

4.認証対象者
| 認証の対象となる木質構造等を製造、製作、販売又は使用するものとします。 ただし、認証の対象者は、一連の認証規範に規定する権利・義務を責任もって遂行し得る能力を有するものであることが条件となります。 |
5.センターの行う他の認証との相違
(1)接合金物に関する認定との関係 接合金物に関する認定の対象となるものは、新工法認証の対象外とします。ただし、接合部分だけでなく、その他の構造部分に作用する応力等を考慮しなければ性能を評価することが困難な場合は、本制度における性能認証の工法となります。 (2)木造建築合理化システム認定との関係 木造建築合理化システム認定は、生産・供給システムの省力化を図るなどの合理化した工法による建築物を認定するもので、標準的な仕様を前提としたものが対象となります。これに対し、本制度の性能認証の工法は、基本的に性能そのものを認証することに主眼が置かれており、一般的には複雑で特殊な工法が対象となります。 (3)AQ認証との関係 AQ認証は、あらかじめ認証品目及びその品質・性能を定めてそれに適合する製品の品質・性能を認証するものです。これに対し、本制度の性能認証の部品・部材は、企業等が開発した個別製品の品質・性能をその都度定める技術基準に基づき、その用途との関係を考慮して個別に認証するものです。 |
◇手数料
| 認証等の手数料は、下表に掲げる額とします。ただし、申請内容の程度により別途加算することがあります。 |
| 項目 | 手数料 | |
㋐認証手数料 | ① 壁倍率及び床倍率等の低減係数α評価 | 880,000円 |
| ② ①以外の評価*1 | 2,750,000円 | |
㋑更新手数料*2 | 330,000円 | |
㋒変更手数料 | ① 規程第12条第2項の変更 | 1,540,000円 |
| ② 評価書の軽微な変更 | 220,000円 | |
㋓試験法評価手数料 | 550,000円 | |
㋔認証書の再交付料 | 11,000円* | |
| *1 ㋐②の評価を行う場合は、㋓試験法評価も含むものとします。 *2 規程第11条の更新申請時に同第12条第2項の変更を行う場合、㋑更新手数料は㋒変更手数料①の額とします。 |
◇規程
| 木造建築新工法性能認証制度の規程類は、以下の構成となっています。 |
◇認証一覧
認証一覧は、こちらから閲覧できます。(PDF形式)(令和4年7月20日更新) |
◇様式類
| 申請様式(WORD) |